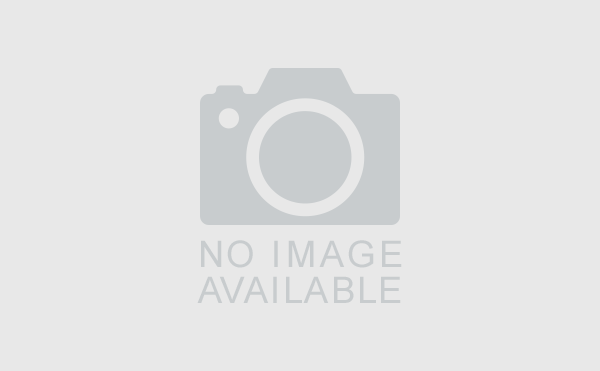日本版DBS(こども性暴力防止法)の仕組みと、行政書士ができる支援
――大阪の保育園・放課後等デイサービス事業者の方へ――
1.日本版DBSとは
日本版DBSとは、子どもと関わる仕事に就く人の性犯罪歴を確認する制度です。
正式名称は、
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」
(令和6年法律第95号)です。
この制度は、児童に対する性暴力やわいせつ行為などの再発を防止し、教育・保育現場の安全を確保することを目的として制定されました。
イギリスなどで実施されている「DBS制度(Disclosure and Barring Service)」を参考にした仕組みで、日本では2025年から段階的に運用が始まります。
2.制度の目的
本制度の目的は、次の二点に整理されます。
- 採用段階での性犯罪歴の確認
子どもと接する職員を採用する際に、過去に児童対象の性犯罪を行っていないか確認する。 - 安全な教育・保育環境の確保
職員研修や体制整備を通じて、性暴力防止への意識を高める。
児童が安心して学び・遊べる環境を整備することが、この法律の根幹にあります。
3.対象となる事業者
確認制度の対象となるのは、子どもに直接関わる教育・保育・福祉事業者です。
- 学校(幼稚園・小中高・特別支援学校など)
- 認定こども園・保育所・幼稚園
- 放課後児童クラブ
- 放課後等デイサービス
- 児童養護施設・障害児入所施設 など
大阪市内や大阪府下でも、私立園・民間デイサービス・小規模保育事業者など、多くの施設が対象に含まれます。
4.事業者に求められる対応
(1)採用時の性犯罪歴確認
新しく職員を採用する際に、性犯罪歴の有無を確認する手続きが必要となります。
確認方法は、法務省等が発行する「性犯罪歴確認証明書」(仮称)をもとに行う予定です。
(2)情報の管理と保護
取得した情報は個人情報として厳重に保管し、他の目的で使用してはなりません。
漏えいや不正利用は厳しく制限されており、違反した場合は罰則が科されることもあります。
(3)職員研修と内部体制の整備
性暴力防止に関する研修を定期的に行い、子どもへの適切な接し方や通報・相談体制を整備することが求められます。
大阪市や大阪府では、今後、研修の実施方法や支援制度が順次発表される予定です。
5.対象となる犯罪の範囲
確認対象となる主な犯罪は以下のとおりです。
- 児童へのわいせつ行為・強制性交等
- 児童買春・児童ポルノ関連犯罪
- 性的虐待その他児童の権利を侵害する行為
刑法、児童福祉法、児童買春・児童ポルノ禁止法などの関連法令に基づき、過去の有罪判決などが確認の対象となります。
6.施行時期と今後の流れ
法律は2025年中に施行予定で、教育・保育分野から順次スタートする見込みです。
施行に合わせ、国から具体的な手続き・申請方法・確認書類の形式が示されます。
大阪府・市町村単位でも、関係機関からの通知や説明会が実施される可能性があります。
7.大阪の事業者が今から準備すべきこと
- 自社(自園・自施設)が対象事業者に該当するか確認する。
- 採用時に「性犯罪歴確認」を行う手続をフローに組み込む。
- 個人情報を安全に管理できる環境を整備する。
- 職員への研修や周知を進め、内部体制を文書化しておく。
8.行政書士が支援できること
日本版DBS制度は、法令遵守・個人情報管理・採用手続など、多くの分野が関わる複雑な制度です。
行政書士は、これらの事務手続きを法令に則って支援する専門家です。
特に以下のようなサポートが可能です。
- 制度の説明・事業者対象確認のサポート
自社が対象かどうかの判断や、今後必要となる手続きの整理を支援します。 - 就業規則・採用手続の整備
新しい制度に対応するための文書(採用時確認規定・個人情報管理規程など)の作成支援。 - 社内研修資料・保護者向け説明文の作成
従業員教育や保護者への周知文書を、制度に沿った形で整備します。 - 行政機関への届出・文書作成支援
今後求められる証明書取得や報告書提出などの行政手続を、書類面からサポートします。
大阪府・大阪市を中心に、保育・福祉・教育関連事業者に向けた制度対応支援を行う行政書士事務所が増えています。
行政手続の専門家に相談することで、施行後のトラブルや手続き漏れを防ぐことができます。
9.まとめ
日本版DBSは、「子どもの安全を守るために、大人側の信頼性を確認する制度」です。
保育園や放課後等デイサービスを運営する大阪の事業者にとっても、採用管理や情報保護の見直しが求められます。
制度の理解と早めの準備を進め、行政書士など専門家の支援を受けながら、安心・安全な運営体制を整えることが重要です。
この内容を、事業者向けの案内資料(Word